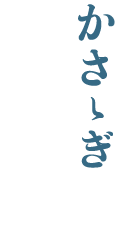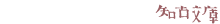初めて文を書いたのは、まだ学生の頃のこと。「雑誌を創るから、なにか書いてみない?」と、軽い調子で誘われた。私はその頃、古典について論文を書こうとテーマを探している途中で、源氏物語を手に取ってみたものの、星の数ほど居る研究者という名の先輩たちに、いたるところ手垢をつけられてしまってばかりな事実に挫折し、なんとか誰も取りくんでいないであろう作品を、論題を捻りだそうと、図書館のできるだけ奥へ奥へ通い、埃の被った古典文学を、気の進まないまま、漁り読んでいるところだった。
そもそも文学部とは名ばかり、レポートでもなければ本など読まないでいたし、役にたちそうにない勉強することで、将来になんの希望をいだいていたのだろう。それなのにもかかわらず、まるでインテリぶって、仰々しい比喩を使ったり、今では誰も使わない旧漢字で手紙を書いたり、偉そうに、文学風を纏っていた。かぶれてしまったのは、特に頑張った訳でもないのに、小さい頃から国語の成績が良かった所為もあるだろう。作文などを書かせてもそつなくこなしていたし、よもや文才があるかのような錯覚を、どこかに持っていた。高校生の時には、ノートの端に詩(のようなもの)を書き、まるで占星術のように、単語を組み合わせることに夢中になっていて、時に〝会心〟といえるようなものができたときには、独り、その秘めごとに酔い、悦に入っていたものだ。大学に入って、谷崎や太宰を読んだあとに、偶然そのときのノートをひきだしの奥で見つけた。そこには、やたらに感傷を煽るだけで、むやみに尖らせただけのことばが、稚拙に並んでいた。おまけに穢い字(自分の字はなんでこんなにも穢く見えるのだろう!)。ノートはすぐに捨ててしまった。
私を同人誌に誘ってきたのは、おなじゼミの男のコだった。あまり話したことのない私に、「いつも、おもしろいレポートを書くから」と云ってきたのだが、嘘だろう。たぶん、彼は私の書いたものなど読んだことがなかった筈だ。思うに、頭数が欲しかったのだ。同人誌とはいえ、文芸雑誌が50ページにも満たないというのは、格好がつかない。今、思えば、内容すらどうでもよかったのかもしれない。彼の理想の―いずれ、メンバーのうちの誰かが有名になり、つられて幾人か、有名でなくとも燻し銀に名を残し、色褪せた表紙が現代文学史の年表に載るような、そんな雑誌を、文豪と冠された先人の真似事をしてみたかっただけなのだ。私が寄せた幾つかの小品も、5号続いた誌面を見ても、ちぐはぐで均衡がとれていなかったし、巻頭の小説と巻末の小説で版面のおおきさが違っているなど、おおよそ信じがたい失敗を犯していたのだ。擁護しておくならば、情熱だけは確かだった。それは、恥ずかしながら、私とておなじだった。
創刊号の表紙には、カササギの絵をつけることになった。この絵は誰が描いたものなのか、彼がいったいどこから持ってきたのか、まったく知らない。意図的だったのか、それともただの思いつきか、「署名を皆、鳥の名前にしよう」と提案された。
メンバーの中に、円い目をした、おとなしい女のコがいた。私と同級生だったと思うのだが、小柄な所為か、ずいぶん年下にみえた。賢治が好きで、童話をテーマに卒業論文を書いたと記憶している。彼はそのコに〝雀(すずめ)〟という名前をつけて、詩をなん篇か書かせていた。〝雀〟ほど敬虔な、彼の信奉者はいなかったように思える。掲載した作品は僅かだったが、ことあるごとに作品を創ってきて、駅のすぐ傍にあった茶色い照明の灯る古い喫茶店で、彼の評価を仰いでいる姿をよく見掛けたものだった。伏せ目がちにはにかみながら、円い目をさらに円くして。立ち上げの頃には熱心に顔を出していたのだが、彼女は夏休み明けに一度顔を見せたきり、なぜだか集まりには来なくなってしまった。
会話は、文字にしたためるよりも日常的な行為だろう。伝達も速い。生活の、実に中心的なコミュニケーションの手段である癖に、いかに嘘で繕っているものか、ありありと判った。文で書くほうが自由になれる、そんな気がしたのはこの頃。話すときは私自身、私のイメージを崩さないように、無意識に繕っている。無意識な癖、実際はかなり緻密に。〝淑やか〟だとか、〝生真面目〟だとか、いかにも化粧を施すように塗りこめて。馬鹿らしいことに、それは、欠点とも思えるようなことですら繕う。〝保守的〟だとか、〝無口〟であったり、それがマイナスともとれるようなことでも、誰かに指摘されると、どこかそれが自分の個性だと思いこんで、〝無口〟に繕ってしまうのだ。
彼は気づいただろうか。あの文に書かれていたのは、あなただったのだと。私が繕っていたのは、主にあなたに対してなのであって、努めてインテリらしい、文学少女を気どってみせていた。好みだと、確信があった。私はあの集会のさなか、あなたが書き、奔らせる鉛筆を、捻る手首の動きを、指のしなやかさばかりを、眺めていた。そして私は、文の中で密かに配役されたあなたを、仮装させ、踊らせることに没頭していた。あるときは賤しい生まれの青年で、貧しく、蔑まれ生きてきたが、ふいに出逢った紳士から本当の両親の名と身分を告げられ、一転、華のような人生を謳歌したり、あるときには酒に溺れ、女に溺れ、欲望の限りを尽くした男で、放蕩のあげく倒れていたところをいたいけな少女に介抱される、そして、実は重く患っていたその少女の病気を治すため、がむしゃらに金を集め、堕落した金に手を出し、さらに闇の稼業へ手を染めていく―そんな、どこかで聞いたような話の数々を。
私は彼の、いったいなにを愛していたというのだろう。だって、彼は私の空想で満たされていただけの存在なのだから。実際の彼のことなど―無口だった私は、集会のたびに交わす事務的なことばと態度で推しはかるのみで、趣味も、生いたちも、実にあやふやだった。あたかも恋に恋していた、ということか。当時の、まだ若い私は、それなりの経験があったとはいえ、いかに猥褻で、不道徳な空想をしているのか、想い悩んだものだ。私の理想と、昂奮と、劣情と、希望と、嗜好の限りを、ただ、皮膚と筋肉を薄く残した、がらんどうな彼の中へ肉詰めして、密かに、活字で愛撫していたのだから。畢竟、愛していたのは―私が創りだした部分を除いてしまえば―彼の肉体以外には、なにもなかったのだから。
彼は、―1歳年上だったのだが―4回生の春過ぎに、あっさりと内定が決まったことを話した。文学へ傾けた情熱はいずこか、おおよそ授業で学んだことなどなんの役にもたちそうにない商社へ。あとで聞いたのだが、それは親戚が関係している会社で、採用にも口利きがあったのだという。
彼は卒業する間際に、同人誌の編集を継いで欲しいと、私に云った。棄てていく文学への想いもあってか、熱っぽく(しかし、身勝手にも思えた)。不埒な理由があったからとはいえ、同人誌の中で一番ページを割いて作品を書いていたのは私だったし、多分、私が一番まともな作品を書いていたからだろう。若く、血の気の多い、青臭い文学議論を延長したままの、うわずった、学生気分に任せて産み落とした作品たちを、私は、私もその構成員でありながら、ことのほか軽蔑していた。まず、彼らとはおなじに見られないよう、そればかりを気にして、作品を創っていただけだったのだが。
新しく編集長になった私は、あっさり同人誌を廃刊にした。黒髪の美しい〝燕(つばめ)〟も、肌の白い〝鷺(さぎ)〟も、声の高い〝鶫(つぐみ)〟も、私が前衛的に導いてくれるものと、期待していたらしい。だけど、興味はなかった。
―帰りに、街中で乳母車を曳いた〝鷸(しぎ)〟と偶然再会した。彼女はあの雑誌の、半ページにも満たないコラムを1度書いたことがあったが、再会した彼女は、同人誌のことなど忘れ、こどもの話を喋り続けていた。
そんなことがあった所為だろうか、押入の奥にしまい込んでいた、埃の黴びた匂いのする雑誌を取りだして―彼は、〝鵲(かささぎ)〟は、今、なにをしているのだろうかと、昔と変わらぬ空想で、想い描いてみる。崩れ落ちるように傾いていった、この不景気の中では、商社に勤めたままで悠々と暮らしているかも怪しい。かといって、私のように、いまでも夢見がちなまま、空想の中だけで独り生きているとも考えにくい。
久し振りに、古い万年筆を取りだして(これは学生のあの頃、なけなしのアルバイト代で買ったもので、決して高価ではないが、今、こうやってなん年ぶりかに取りだしても、十分使える良いものだ)、また、鳥の記憶の続きを綴ってみる。空想の先に浮かんできたのは、やはり彼の物語で、記憶にへばりついた彼よりも、幾分おとなびた、どこかで過ごしているであろう姿を想って書いた。しかし、彼の、私の筆に掛かった描写は、やはり現実とはさかしまに、まるで薄皮一枚挿んでぼやけたような、それでいて妙にリアリティのある銅版画のような、嘘より偽物っぽい出来になってしまった。時を経て褪せてしまった写真、黄ばんだ硝子越しの風景。なん年経っても渝れない、相変わらず腑甲斐ない私の文章力に、嗤いしか出ない。いや。私が書いてきたものなど、所詮、見せかけなのだ。昔から嘘ばかりを書いてきた。こうやって、澱んだ光に照らしだされた、彩度のちぐはぐな風景を描いていることに、なんの疑問があるのだろうか。昔も今も、私は嘘で固めて、繕っているだけのことじゃないか。
彼は私を憶えているだろうか。私はいま、どこかで息を潜めて忍んでいるかのようにも思える姿を想う。昔のおもかげをどれだけ残しているだろうか。あの時、文学に投じていた情熱は、今、なにへ向かっているのか。いや、それよりも、私は、私の期待は―彼は今でも私の右脳を火照らすような精悍な姿をしているだろうか。いや、歳を重ねるごとに、より端然として、いや、―止めておこう。やはり、あれはあれで、私が肉づけした、ただの男の骨格でしかないのだ。魅力的な容姿をしただけの男ならば数多、街中で、電車の中でだって見つけられるだろう。頭の中で肥やすのならば、誰だって構わない。ただ、ノスタルジーが、飴玉の糖の濁った半透明の記憶が、黄ばんだパラフィン紙に透けた風景が、彼の、やや柔軟に曲がる手首をより濃艶に思いださせる。しかし―くどくも―嘘なんだ。抓んで剥がしていける、薄いセロファン状の、べたつきの残る記憶。紗幕を透した先は、全部私が描いたものなんだ。詰まるところ、私は彼を愛したことも、話したことすらなかったのだろう。ある日、薄暗い図書館の閲覧室で、古典文学の厳つい文法に倦み、気晴らしに手にした図鑑に載っていた、カササギの写真の雄々しさに触発された、その時、見上げた先にいた男の顔が、雄の黒鳥のように逞しくて、直感的に物語を、頽廃と官能の文学的なロマンティズムを、想い描いただけなんだ。いや、もしかして話をしたかもしれない。彼は確かにおなじゼミで、近代文学の文学史年表に等間隔に印をつけ、年代から数学的な法則と文学の傾向を結びつけて比較するなど、いささか児戯めいた銘題を打ちたてていた。いや、それすらも怪しく思える。なにか、私の好きな、空想的なエピソードで、自分自身の記憶の上書きを、不透明の、塊く練った絵の具で塗り潰してしまっただけかもしれない。久し振りに訪れた場所が、思い出の中のまばゆさとは程遠い、鈍い輝きしか持っていなかったような記憶の美化、忘却の美化を、それこそ空想の中でしていたのかもしれない。
少なくとも、私は彼となにもなかったのだ。私は彼を本当に愛していたかもしれないし、もしかして、彼も私を―既に文体も、漢字も古臭くなってしまった時代遅れの文学ばかり探している、口数の少ない無愛想な女のコを―好いていてくれたのかもしれない。しかし、なにもなかったんだ。交わることも、手が触れあったことさえも。肉体のなかった彼は、やはり空想上の生き物に過ぎないのだ。
口にした炭酸水のグラスを、雑誌の上に置いてしまい、古びた紙に、円い滲み跡が浮かんだ。暈けるインクを見て、それをゴミ箱へと捨てた。この原稿用紙も一緒に捨ててしまおうかと、いや―思いかえして、1枚目にさかのぼり、題名の脇に署名を入れることにした。昔とおなじ―〝鵤(いかるが)〟と。